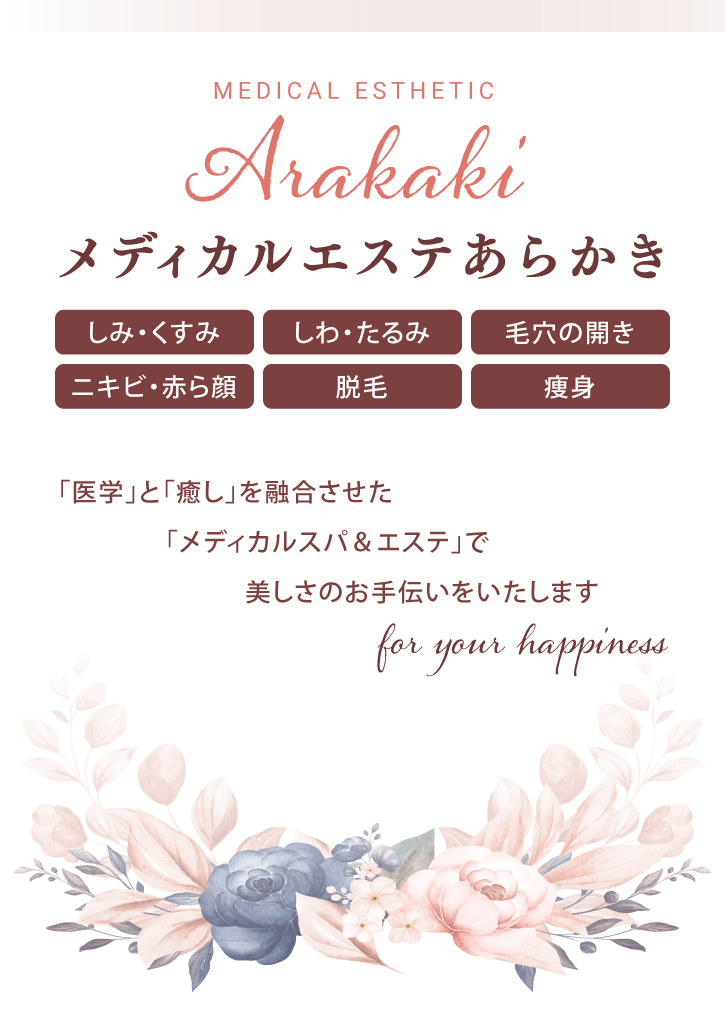採用情報
当クリニックでは一緒に働くスタッフを募集しています。詳細はお問い合わせください。
看護師(常勤)
募集職種
看護師(常勤)
募集人数
1名
勤務地
新垣形成外科〒901-2227 沖縄県宜野湾市宇地泊2-24-22
勤務時間
8:30〜18:00(休憩時間90分)、(土曜日)
8:00~17:00(休憩時間60分)
仕事内容
手術室直接介助・麻酔介助・診療補助・医療レーザー介助・処置介助・採血・点滴・水光注射施術
給与
20〜35万円/月(時間外手当あり)※試用期間あり(3ヶ月〜6ヶ月) 准看護師:時給1,350円~ 正看護師:時給1,500円~
資格
正・准看護師未経験者歓迎
待遇・福利厚生
交通費支給・昇給年1回・賞与年2回・時間外手当あり社会保険完備・各種手当あり・制服貸与
休日休暇
完全週休2日制(木・日・祝日)・年末年始休暇・有給休暇・慶弔休暇※有給消化率100%
医療事務
募集職種
医療事務スタッフ(常勤)
募集人数
1名
勤務地
新垣形成外科〒901-2227 沖縄県宜野湾市宇地泊2-24-22
勤務時間
8:30〜18:00(休憩時間90分)、(土曜日)
8:00~17:00(休憩時間60分)
仕事内容
受付事務
給与
17〜21万円/月※試用期間あり(3ヶ月〜6ヶ月)時給1,200円
資格
不問※経験者優遇
待遇・福利厚生
交通費支給・昇給年1回・賞与年2回・時間外手当あり社会保険完備・各種手当あり・制服貸与
休日休暇
完全週休2日制(木・日・祝日)・年末年始休暇・有給休暇・慶弔休暇※有給消化率100%
毛髪ケアスタッフ
募集職種
毛髪ケアスタッフ(常勤)
募集人数
1名
勤務地
(株)あらかき美容医学研究所(ヘアクリニック新垣)〒901-2227 沖縄県宜野湾市宇地泊2-24-22
勤務時間
8:30〜18:00(休憩時間90分)、(土曜日)
8:00~17:00(休憩時間60分)
仕事内容
洗髪・毛髪顕微鏡検査・育毛、発毛ケア・カウンセリング・指導など※パソコン操作(ワード・エクセル・パワーポイント)
給与
17〜21万円/月※試用期間あり(3ヶ月〜6ヶ月)時給1,200円
資格
不問※美容師・理容師優遇
待遇・福利厚生
交通費支給・昇給年1回・賞与年2回・時間外手当あり社会保険完備・各種手当あり・制服貸与
休日休暇
完全週休2日制(木・日・祝日)・年末年始休暇・有給休暇・慶弔休暇※有給消化率100%
サプリメントスタッフ
募集職種
サプリメントスタッフ(常勤)
募集人数
1名
勤務地
(株)あらかき美容医学研究所〒901-2227 沖縄県宜野湾市宇地泊2-24-22
勤務時間
8:30〜18:00(休憩時間90分)、(土曜日)
8:00~17:00(休憩時間60分)
仕事内容
分子栄養学補助・サプリメントの在庫管理・顧客管理※パソコン操作(ワード・エクセル・パワーポイント)
給与
17〜21万円/月※試用期間あり(3ヶ月〜6ヶ月)時給1,200円
資格
不問※未経験者可 栄養に関心のある方
待遇・福利厚生
交通費支給・昇給年1回・賞与年2回・時間外手当あり社会保険完備・各種手当あり・制服貸与
休日休暇
完全週休2日制(木・日・祝日)・年末年始休暇・有給休暇・慶弔休暇※有給消化率100%
エステスタッフ
募集職種
エステティシャン(常勤)
募集人数
1名
勤務地
(株)あらかき美容医学研究所〒901-2227 沖縄県宜野湾市宇地泊2-24-22
勤務時間
8:30〜18:00(休憩時間90分)、(土曜日)
8:00~17:00(休憩時間60分)
仕事内容
メディカルエステ・美顔ケア・脱毛・カウンセリング・顧客様への指導
給与
17〜21万円/月※試用期間あり(3ヶ月〜6ヶ月)時給1,200円
資格
不問※経験者優遇
待遇・福利厚生
交通費支給・昇給年1回・賞与年2回・時間外手当あり社会保険完備・各種手当あり・制服貸与
休日休暇
完全週休2日制(木曜他シフトによる休み)・祝日もシフトによる休みあり・年末年始休暇・有給休暇・慶弔休暇※有給消化率100%